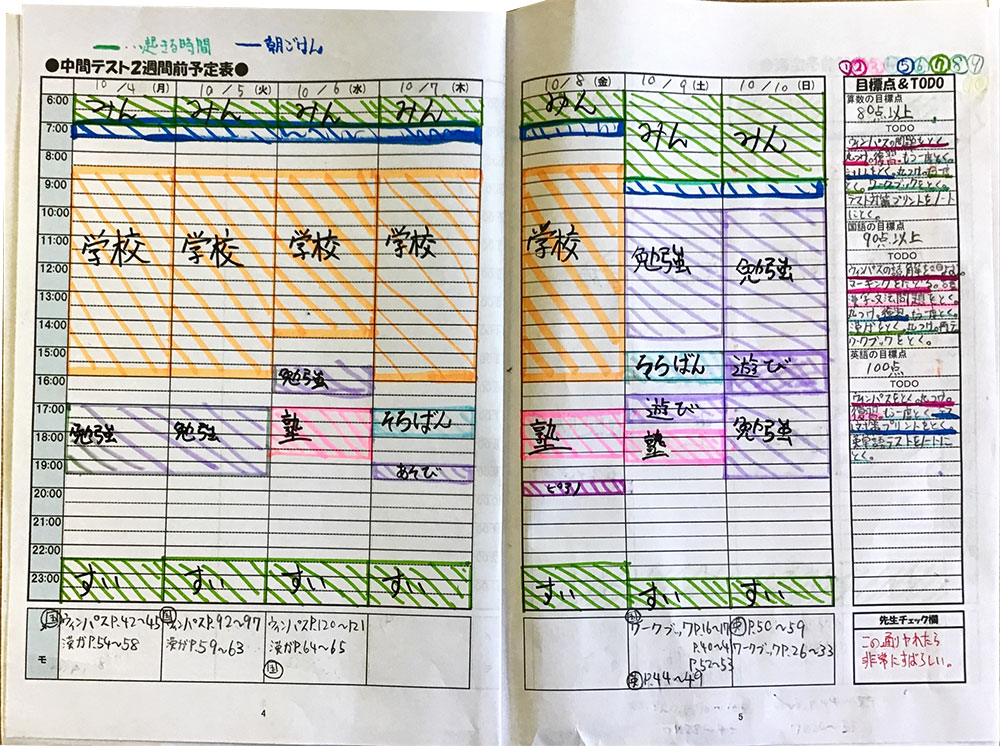奈良学園中学校の概要
奈良学園中学校は昭和54年(1979年)に創立された中学校です。
医進コースと特進コースの2種類のコースを設けており、中学1・2年生では混合で学習を実施したのち、中学3年生より各コースに分かれます。
来る大学入試を見据え、早め早めに進路選択に必要な情報を提供。
一人ひとりの目標達成のために丁寧な指導を実施します。
ほかにも高校から外部募集する「理数コース」もあります。
奈良学園高校からの大学進学実績について、国公立大学医学部への進学や難関私立大学へ多くの卒業生を輩出しています。
校風
自学自習の習慣をつくるため、中学1・2年生に自習会を開いたり、勉強がしやすくなる基礎トレーニングなども実施されます。 そのため、生徒は自主的に物事に取り組む習慣を身に着けていきます。 また中学3年生では、東大研修会や京大研修会など卒業生によるキャンパス案内と大学の先生による講義を受講し、大学受験に対するサポートが手厚いのが特徴です。
教育方針
『未来を創造する豊かな「人間力」の養成』を教育目標として掲げており、「学力・自主性・協調性・体力」をバランスよく育成。未来を創造するたまに豊かな「人間力」を養います。
■ 奈良学園中学校公式HPはこちら
お問い合わせ先
TEL 0743‐54-0351
FAX 0743-54-0335
所在地
〒639‐1093
奈良県大和郡山市山田町430
アクセス方法
JR大和路線「大和小泉」からバス15分
近鉄橿原線「近鉄郡山」からバス25分
近鉄奈良線「学園前」からバス35分
奈良学園中学校(2025年度)の入試情報
入試情報
奈良学園中学校の入試対策の特徴
奈良学園中学校の入学適性検査は、2科(国語・算数)・3科(国語・算数・理科)・4科(国語・算数・理科・社会)の3種類の適性検査の中から選択できます。
奈良学園中学校
令和7年度(2025年度)入試結果(平均点・倍率等)
定員と倍率
奈良学園中学校は二つのコースがあり、難関大学を目指す特進コースと医学部を目指す医進コースがあります。
募集人員は、特進コースが125名、医進コースが35名です。 以下、令和7年度(2025)年度の入試結果です。
| 募集人員 | 入試日程 | コース | 性別 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ・特進 125 ・医進 35 | A日程 | 特進 | 男子 | 42 | 21(39) |
| 女子 | 16 | 7(24) | |||
| 医進 | 男子 | 63 | 13 | ||
| 女子 | 39 | 8 | |||
| B日程 | 特進 | 男子 | 59 | 34(64) | |
| 女子 | 38 | 23(40) | |||
| 医進 | 男子 | 119 | 45 | ||
| 女子 | 61 | 11 | |||
| C日程 | 特進 | 男子 | 33 | 7(37) | |
| 女子 | 14 | 7(20) | |||
| 医進 | 男子 | 61 | 12 | ||
| 女子 | 37 | 7 |
※合格者の()内の数は、回し合格での合格者数。
合格者平均点と最高点
令和7年度(2025年度)の合格者平均点は、A・B・C日程それぞれ以下の通りとなりました。
各日程とも、国・算は 60分・各150点満点、理・社は40分・各100点満点になります。
(A日程・B日程の医進コースについては、理科の配点を150点満点に換算)
A日程の合格者平均点と最高点
| 国語 (150点満点) | 算数 (150点満点) | 理科 (特100点満点 /医150点満点) | 社会 (100点満点) | 総合 (特500 /医550) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均点 | 特進 | 102.2 | 107.7 | 60.6 | 69.3 | 342.7 |
| 医進 | 112.4 | 135.5 | 110.7 | 79.7 | 441.0 | |
| 最高点 | 特進 | 135 | 134 | 79 | 89 | 390.0 |
| 医進 | 134 | 150 | 130.5 | 92 | 476.5 | |
※特進コース平均点は、第2希望での合格者を含めた平均点である。
※特進コース最高点は、特進コース第1志望者のみの最高点である。
B日程の合格者平均点と最高点
| 国語 (150点満点) | 算数 (150点満点) | 理科 (特100点満点 /医150点満点) | 社会 (100点満点) | 総合 (特500 /医550) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均点 | 特進 | 103.6 | 92.3 | 62.5 | 76.6 | 334.2 |
| 医進 | 115.2 | 123.5 | 114.7 | 84.2 | 437.9 | |
| 最高点 | 特進 | 130 | 142 | 81 | 95 | 410.0 |
| 医進 | 140 | 150 | 136.5 | 99 | 483.4 | |
※特進コース平均点は、第2希望での合格者を含めた平均点である。
※特進コース最高点は、特進コース第1志望者のみの最高点である。
C日程の合格者平均点と最高点
| 国語 (150点満点) | 算数 (150点満点) | 総合 (300点満点) | ||
|---|---|---|---|---|
| 平均点 | 特進 | 101 | 90.7 | 191.7 |
| 医進 | 114.8 | 120.2 | 235 | |
| 最高点 | 特進 | 127 | 112 | 208 |
| 医進 | 133 | 150 | 283 | |
※特進コース平均点は、第2希望での合格者を含めた平均点である。
※特進コース最高点は、特進コース第1志望者のみの最高点である。
過去の入試結果
奈良学園中学校
入学者の選抜方法について
A日程・B日程の受験科目は、国語・算数・理科・社会となり、3教科型(国語・算数・理科)もしくは4教科型(国語・算数・理科・社会)のどちらかを出願時に選択します。
配点は、国語・算数が各150点満点、社会は100点満点。
理科は、特進コースは100点満点となり、医進コースは150点換算となります。
C日程は、国語・算数の2教科型で、各150点満点で合計300点満点となります。
奈良学園中学校
出題形式
令和7年度(2025年度)入試
【国語】
(150点満点・60分)
1.「空所補充」が頻出
「本文」「本文内容を説明した文」の「空所補充」の問題が多いです。
特に「本文内容を説明した文」の空所補充は、①空所を設けた文の文脈の理解、②「解答の材料となる本文中の部分」を的確につかむ、という二つの力がためされます。
単純な「○○字以内で説明しなさい」という設問に比べると、「解答に入れるべき内容・表現(キーワード)」が限定されるため、受験においては、得点差を決定づける設問となります。
2.物語は「やや難」
「課題を乗り越えてのハッピーエンド」というような単純なストーリーではなく、なんらかの葛藤を抱えた主人公の細かな心の動き(および、それを表現する作者の表現意図)を読み取る必要のある作品が本文であることが多いです。
その点で、物語の難易度は高いといえます。
3.知識問題は「定型」となっている
大問3の出題内容(設問数・構成)は、直近三か年でまったく同じです。
よって、「四字熟語」「慣用句」「語彙」「漢字」は、奈良学園受験においては必須の学習です。
(下記の表は、A日程の出題内容)
| 大問1 | 本文内容 | 物語(高山環『夏のピルグリム』より) 少女がひと夏の一人旅を通して自己を再生する物語の一場面 |
| 問1 | 指示語の指示内容(記述問題) | |
| 問2 | 心情説明(発言の理由・選択肢問題) | |
| 問3 | 本文中の空所補充(選択肢問題) | |
| 問4 | 心情の根拠の説明(記述問題) | |
| 問5 | 心情説明(発言の理由・選択肢問題) | |
| 問6 | 心情説明(傍線部の心情の説明として適切な二字熟語・選択肢問題) | |
| 問7 | 心情説明(発言の理由・選択肢問題) | |
| 大問2 | 本文内容 | 論説文(戸谷洋志『悪いことはなぜ楽しいのか』より) 「悪意」の本質について述べる内容 |
| 問1 | 本文中の空所補充(2問・「〇〇的」という言葉を選ぶ選択肢問題) | |
| 問2 | 傍線部の言い換え(選択肢問題) | |
| 問3 | 指示語が指す内容(記述問題) | |
| 問4 | 本文中の空所補充(選択肢問題) | |
| 問5 | 傍線部の具体的説明(記述問題・25字以内) | |
| 問6 | 修飾・被修飾の関係(「いつしか」がかかる部分を選ぶ選択肢問題) | |
| 問7 | 会話文の中から本文内容に合致する発言者を選ぶ問題(選択肢問題) | |
| 問8 | 傍線部の理由を説明した文の空所を補充する問題(記述問題・10字程度+25字程度) | |
| 大問3 | (A)問1 | 四字熟語(選択肢問題) |
| (A)問2 | 慣用的表現(「□に鶯」の空所に漢字一字を入れる) | |
| (A)問3 | 語句の意味(選択肢問題) | |
| (A)問4 | 語句の意味(選択肢問題2問) | |
| (B) | 漢字の書き(8問)読み(2問) |
奈良学園中学校
入試対策ポイント
【国語】入試対策
1.物語:「人物像(とその葛藤)」「人物像に基づく『心情』」の把握
「『葛藤(AとBの対立)』を乗り越えた主人公の『変化』」は中学受験での物語の「定番」ではあります。
ただし、多くの場合は「変化」にスポットを当てた出題となるのに対して、奈良学園の場合は「葛藤」にスポットを当てる傾向があります。
よって、普段の読解でも「この主人公はAである一方でBである」「この場面での心情はAである一方でBである」というように、人物像・心情を「二面」からとらえる読みの習慣を持っておきましょう。
2.論説文:「論旨把握意識」を持って読むことの習慣化
「傾向」で述べたように「本文を説明した文の理解」も求められます。
この場合、「本文の論旨は…である」「この説明文はその論旨を…という観点で説明している」「よって空所補充は本文の…を材料とする」という「論理的思考」が必要です。
この思考をスムーズに行えるようにするためには、普段から「本文全体の論旨は…である」「その論旨を読者に伝えるために、この段落では…という観点(考え)を示している」というように、文章を「論理的・分析的」に読む習慣をもつことが大切です。
3.「自分の言葉」で表現する訓練
記述問題は自分で表現を工夫しなければならないレベルであり、普段から頭で理解したことを言葉で表す習慣を持つことが重要です。
また、問題を解く練習だけでなく、授業中のしっかりした発言を積み重ねていくことで、長い記述問題でもきちんと自分の言葉で埋める力が身についていきます。
4.知識領域の反復学習
漢字、語句については難しめの問題が目立つため、日頃から問題演習を欠かさず行うことが重要です。
漢字ガイダンスやSUCCESS・魔法のノート・季節講習テキストの知識ページ、実力テストの勉強など、日々の学習が入試に直結していることを忘れずに取り組むことが合格への道です。
KECの奈良学園中学校
対策講座・模試情報
★奈良学園中学校模試
小6生を対象に問題に決められた時間内で取り組む経験と、解説授業の受講を通して、実戦力を高めます。
また、模擬試験受験後に返却される成績表は、その後の学習方針を定めるために、役立てることができます。
KECの合格メソッドについて詳しくみる
こちらをご覧ください。
奈良学園中学校の合格者の声
113 ゼミ桜井)大阪教育大学附属天王寺中学校 /奈良学園中学校(特進コース) 合格
奈良学園中学校/奈良学園登美ヶ丘中学校 合格
奈良女子大学附属中等教育学校/奈良学園中学校(特進コース)/奈良学園登美ヶ丘中学校(Ⅰ類)/帝塚山学院中学校(ヴェルジェ[エトワール]コース) 合格
奈良学園中学校(特進コース)/聖心学園中等教育学校(英数Ⅰ類コース) 合格
奈良女子大学附属中等教育学校/大阪教育大学附属天王寺中学校/奈良学園中学校(特進コース)/奈良学園登美ヶ丘中学校(Ⅰ類) 合格
奈良学園中学校(特進コース)/奈良学園登美ヶ丘中学校(Ⅱ類)/聖心学園中等教育学校(英数Ⅰ類コース) 合格
その他の中学の入試対策ページを見る
大阪教育大学附属天王寺中学校(大教大天王寺)の入試対策は、下記からご覧いただけます。