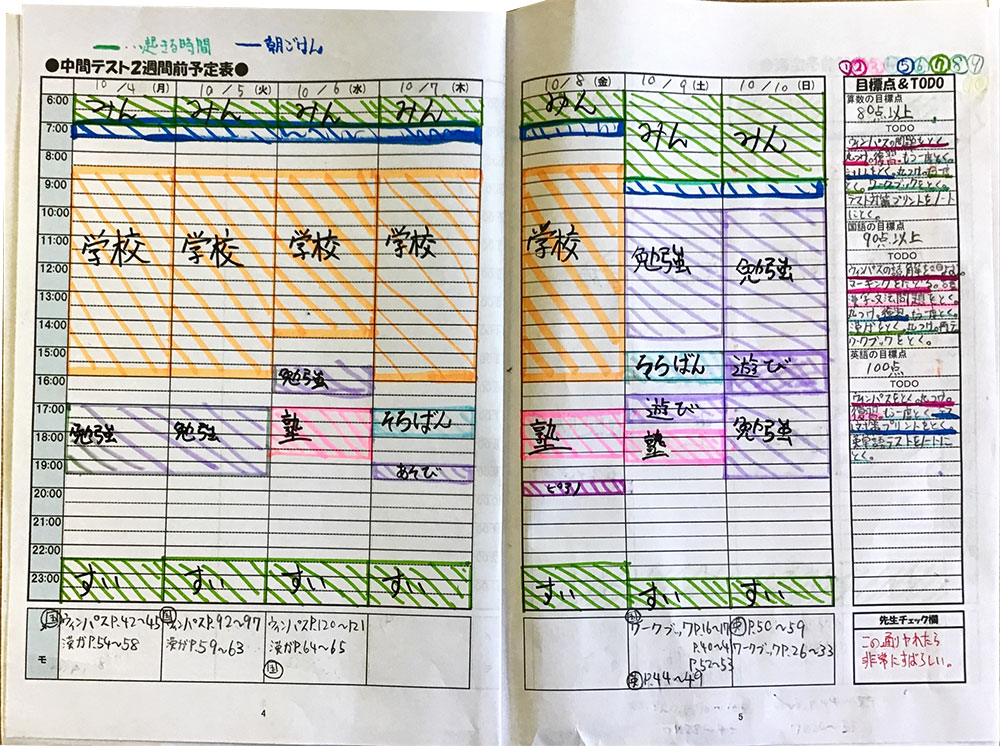奈良教育大学附属中学校の概要
奈良教育大学附属中学校は、奈良県唯一の国立大学法人の附属中学校です。
附属大学との連携はもちろん、地域の教育委員会とも協働しながら、学校の課題を解決するため実験的で、周りをリードするような取組を開発し、実施しています。
また教育実習プログラムの開発とその改善にも力を入れています。
中学卒業後の進路として、奈良・畝傍・郡山を始めとした難関国公立高校や難関私立高校へ多く輩出しています。
校風
教育目標に「科学と技術の基本を身につけ、すすんでものの本質をきわめる人間に」とあるように、さまざまな物事に生徒全員がチャレンジしています。特に部活動の一つである科学部は、国際ロボットコンテストで2年連続の日本一になるなど科学を通して活躍している生徒もいます。
教育方針
・真理を求め、平和を願い、しあわせな世の中を築く人間に ・科学と技術の基本を身につけ、すすんでものの本質をきわめる人間に ・自由と責任を重んじ、粘り強く現実を切り開く人間に ・みんなのいのちや願いを大切にし、あい励まし合い助け合う人間に ・豊かなこころとたくましいからだをもち、明るく健やかに生きる人間に この5つを教育目標として掲げています。
■ 奈良教育大学附属中学校公式HPはこちら
お問い合わせ先
TEL 0742-26-1410
FAX 0742ー26-1413
所在地
〒630-8113
奈良県奈良市法蓮町2058-2
アクセス方法
JR「奈良」駅から奈良交通バス「航空自衛隊」「西大寺駅」行きに乗り約10分後「教育大附属中学校」下車、北へ徒歩約10分
近鉄「新大宮」駅から北東へ徒歩約20分
奈良教育大学附属中学校(2025年度)の入試情報
入試情報
奈良教育大学附属中学校の入試対策の特徴
令和4年度入試より、社会・理科の検査を「総合」とし、面接を実施すると変更されました。これに伴い、理科・社会だけでなく国語・算数についても、これまでの入試傾向が変更される可能性があります。
よって、過去問に取り組むだけでなく、総合的に力をつけておく必要があります。
奈良教育大学附属中学校
令和年7度(2025年度)入試結果について
定員と倍率
奈良教育大学附属小学校からの連絡進学者を含んだ募集人数は、120名です。
一般受検については、実質競争倍率1.7倍となりました。
| 募集 人員 | 出願 者数 | 受検 者数 | 合格 者数 | 実質 倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 120 | 244 | 150 | 88 | 1.7 |
| 附属小 | 56 | 56 | 56 | 1.0 |
合格者平均点
2025年度入試の一般受検者の合格者平均点は、100点満点中75.8点となりました。
合格者の最低点は、69点でした。
過去の入試結果
奈良教育大学附属中学校
入学者の選抜方法について
奈良教育大学附属中学校の学力検査は、
- 国語(40分)
- 算数(40分)
- 総合(社会・理科)(60分)
- 面接(10分)
の4科目で実施されます。
奈良教育大学附属中学校
令和7年度(2025年度)出題形式
国語
1.内容は変化なし・難易度は「やや易化」/「『知識領域』・『問われ方』への対応力」が求められる
「問題数」「小問の内容」などは2023・2024年度の入試と同様でした。
ただ、作文の指定字数が180~200字(過去2か年は240~300字)と減少したことから、試験全体のボリュームという点では「やや易化」したといえます。
知識領域については、2024年度が「敬語」「熟語の構成」、2025年度は「助動詞・助詞」「ことわざ・慣用句」が出題され、「知識分野全体から何かを出題する」という方針であると考えられます。
読解問題については、(4)~(10)のように「論旨把握を試す設問」という共通点はありながらも「質問の仕方(問い方)」に変化を持たせています。
2.作文問題のテーマは年度によって異なる
2023年度:マスクをしてのコミュニケーションの問題点+コミュニケーションで大切だと思うこと
2024年度:おすすめの本について、その本の紹介+どのような人に(どのようなときに)読むことをすすめるか
2025年度:言葉の力を感じた出来事の状況説明+その経験を生かしたいことや、その経験からの学び
作文問題が復活してから3年になりますが、上記のように「作文のテーマ」は変化しつづけています。
2026年度以降も「様々な出題」に対する対応力が試されると考えられます。
30点満点(40分)
| 大問1 | (1) | 漢字書き取り(2問) |
| (2) | 漢字の読み(2問) | |
| (3) | 主語を選ぶ問題(選択肢問題・3問) | |
| (4) | 論説文(鷲田清一『わかりやすさはわかりにくい?――臨床哲学講座』より) 内容:「他者の理解」「ほんとうのコミュニケーション」とはどのようなものかを指摘する内容 | |
| 大問2 | 本文内容 | 論説文(森毅『まちがったっていいじゃないか』より) 内容:「自分を大事にする」「目的にしばられない」という観点で現代社会を生きるためのヒントについて述べる内容 |
| (1) | 接続語の補充(選択肢問題・3問) | |
| (2) | 脱文補充(設問で提示された文章が本文中のどこに入るかを答える・選択肢問題) | |
| (3) | 同内容表現(傍線部と同内容の表現を本文中から探す・書き抜き問題) | |
| (4) | 論旨把握(傍線部に対しての筆者が感じていることを答える・書き抜き問題) | |
| (5) | 論旨把握(傍線部の原因や指示語内容をおさえる・書き抜き問題) | |
| (6) | 同内容表現(傍線部と同じ意味で用いられている表現を本文中から探す・書き抜き問題) | |
| (7) | 論旨把握(傍線部の原因をおさえる・書き抜き問題) | |
| (8) | 論旨把握(傍線部に対しての筆者の考えとして適切なものを選ぶ・選択肢問題) | |
| (9) | 論旨把握(傍線部の説明として適切なものを選ぶ・選択肢問題) | |
| (10) | 論旨把握(筆者が述べていないことを選ぶ・選択肢問題) | |
| 大問3 | 作文 | 「言葉の力を感じた出来事」という題名で作文する。 ・二段落で書く 第一段落は「言葉の力を感じた出来事」と「そのときの状況」を書く。 第二段落は「その経験を生かしたいこと」あるいは「その経験から学んだこと」を書く。 ・180字以上200字以内 |
奈良教育大学附属中学校 入試対策ポイント
国語 入試対策
知識定着と基本動作の徹底(確実な解答を実現するために)
① 「知識」「読解」のバランス良い学習をする
「慣用句」「熟語の構成」など、知識領域は様々な分野がありますが、その一つひとつを確実に自分のものとする継続的な努力が必要です。
読解については、「本文マーキング」「質問文マーキング」「選択肢の○✕マーキング」を習慣化し、「確実に本文を読む」「確実に質問内容をつかむ」「確実に選択肢を見極める」という姿勢を持ち、「取りこぼしのない解答」ができる力を身につけましょう。
② 「自分の考え」を「相手に伝わるように」書く作文練習をする。
作文は、「なんとなく思いつくまま書く」という書き方では、「伝わらない」「途中で行き詰まる」ということにつながります。
よって、作文練習の際には次の3つの習慣を持つように心がけましょう。
⑴「自分の考えは〇〇だ」を整理すること
⑵「自分の考えを伝えるためには~という構成で書くべきだ」という思考を持つこと
⑶「主語・述語」を意識して文を書くこと
KECの奈良教育大学附属中学校
対策講座・模試情報
表現講座
「表現力」養成のKECの専門授業です。
この講座では、「表現力」を身につけるために必要な3つの力を養います。
- 本文や複数の資料から示される事実を正確に読み取る「読解力」
- 自分の意見やその理由を的確に伝える「伝達力」
- 質問や反論に対して瞬時に解答を導くことができる「現場思考力」
模試
令和3年度入試より変更された出題形式に対応した試験構成で実施しております。
1点の重みが非常に大きい奈良教育大附属中学校入試を突破するためのノウハウが詰まった解説をお伝えいたします。
KECの合格メソッドについて詳しくみる
こちらをご覧ください。
奈良教育大学附属中学校の合格者の声
奈良県立青翔中学校 /奈良教育大学附属中学校 合格
京都橘中学校(Vコース)/奈良教育大学附属中学校 合格
京都橘中学校(Vαクラス)/奈良教育大学附属中学校 合格
京都教育大学附属桃山中学校/奈良教育大学附属中学校 合格
奈良市立一条高等学校附属中学校/奈良教育大学附属中学校/奈良学園登美ヶ丘中学校(Ⅱ類)/育英西中学校(立命館コース) 合格
京都橘中学校(Vαクラス)/奈良教育大学附属中学校 合格
その他の中学の入試対策ページを見る
大阪教育大学附属天王寺中学校(大教大天王寺)の入試対策は、下記からご覧いただけます。