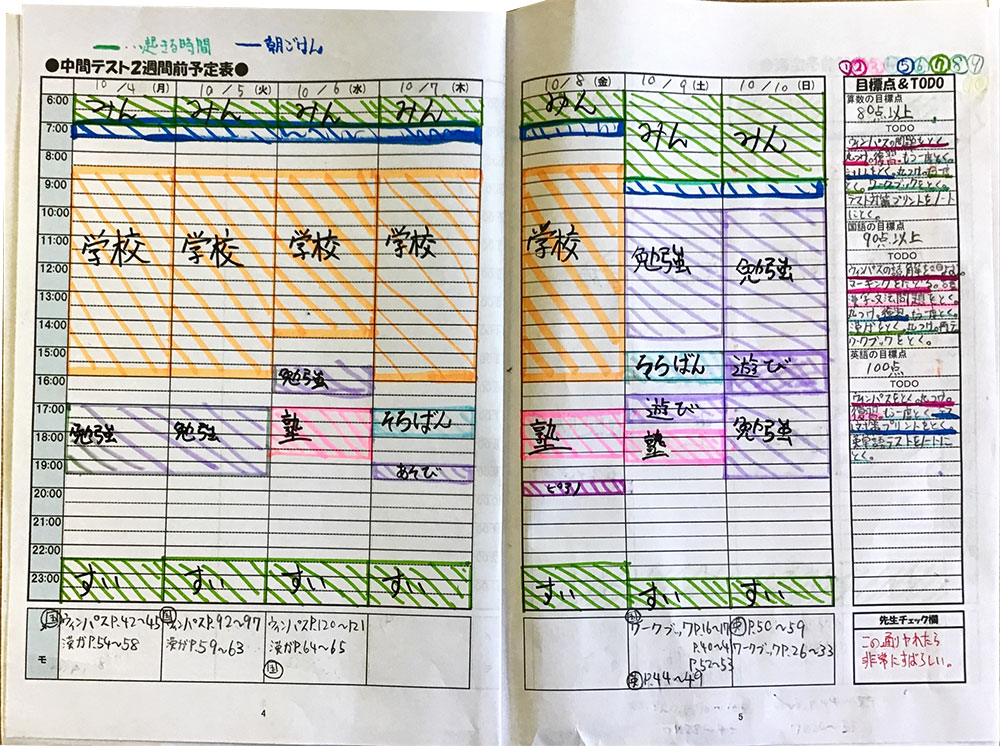奈良学園登美ヶ丘中学校の概要
奈良学園登美ヶ丘中学校は、平成20(2008)年4月に創立されました。
男女共学で、奈良学園登美ヶ丘高等学校と合わせて中高6年一貫教育を行います。
「子どもの『伸び率』日本一を目指す」という学校経営スローガンのもと、大学受験に必要な総合的学力である「学び力」、学問の面白さを追究する能力である「探究力」、世界とつながる行動力である「国際力」、そしてそれらの力を総合した、自立した社会人として生きる力である「人間力」の養成に力を入れています。
校風
校訓の「尚志・仁智・力行」は、志を高くし(尚志)、思いやりの心と知恵を持って(仁智)、何事にも努力して行うことを意味しており、常に自分の夢と希望を大切にし、相手を思いやる心情と豊かに生きる知恵を身につけ、汗を流し、感動に涙する生徒たちの育成を行っています。また、幼稚園児から高校生までが一緒に過ごすキャンパスであることから、年少の者や困っている者への思いやりの心、年長の者への憧れや敬意の気持ちが自然に醸成される環境が整っています。
教育方針
建学の精神「自ら生きて・活きる」を礎として、「和の精神」を大切にし、「逞しく生きる力」を育み、「科学的に物事を見る力」を身につけることを教育の目標にしています。
お問い合わせ先
◆奈良学園登美ヶ丘総合事務室
TEL:0742-93-5111(代表)
FAX:0742-47-9922
URL:https://www.naragakuen.jp/tomigaoka/t_jun/
所在地
〒631-8522
奈良市中登美ヶ丘3-15-1
アクセス方法
・近鉄けいはんな線「学研奈良登美ヶ丘」駅 徒歩8分
・奈良交通バス「奈良学園登美ヶ丘」(近鉄奈良線「学園前」駅から8分)下車 徒歩すぐ
・奈良交通バス「北登美ヶ丘1丁目」(近鉄奈良線「学園前」駅から10分、近鉄京都線「高の原」駅から15分)下車 徒歩3分
奈良学園登美ヶ丘中学校(2025年度)の入試情報
入試情報
奈良学園登美ヶ丘中学校の入試対策の特徴
奈良学園登美ヶ丘中学校の入学試験は、A日程は3科(国語・算数・理科)・4科(国語・算数・理科・社会)の2種類から選択できます。
B日程・C日程は2科(国語・算数)の試験です。
奈良学園登美ヶ丘中学校
令和7年度(2025年度)入試結果について
| 日程 | 種別 | 志願者 | 欠席者 | 受験者数 | 合格者数 | |
| A日程 | 専願 | 114 | 2 | 112 | Ⅰ類 20 | Ⅱ類 62 |
| 併願 | 55 | 1 | 54 | Ⅰ類 15 | Ⅱ類 19 | |
| 合計 | 169 | 3 | 166 | Ⅰ類 35 | Ⅱ類 81 | |
| 日程 | 種別 | 志願者 | 欠席者 | 受験者数 | 合格者数 | |
| B日程 | 全 | 362 | 65 | 297 | Ⅰ類 54 | Ⅱ類 174 |
| 日程 | 種別 | 志願者 | 欠席者 | 受験者数 | 合格者数 | |
| C日程 | 全 | 139 | 54 | 85 | Ⅰ類 8 | Ⅱ類 48 |
合格者平均点・受験者最高点・受験者平均点
| 日程 | 種別 | 国語(120) | 算数(120) | 理科(80) | 社会(80) | 換算(400) | |
| A日程 | 専願 | 受験者最高点 | 107 | 89 | 73 | 70 | 339 |
| 専願 | 合格者平均点 | 82.5 | 53.0 | 46.2 | 54.2 | 241.8 | |
| 併願 | 受験者最高点 | 105 | 94 | 71 | 74 | 319 | |
| 併願 | 合格者平均点 | 88.2 | 55.0 | 51.0 | 59.7 | 263.0 | |
| 全 | 受験者平均点 | 80.0 | 47.0 | 43.3 | 51.0 | 226.6 |
3教科型受験は、3教科の合計の1.25倍を、4教科型受験は3教科(国・算・理及び国・算・社)の合計の1.25倍と4教科の合計のうち最も⾼い得点を換算点とする。
| 日程 | 種別 | 国語(120) | 算数(120) | 合計(240) | |
| B日程 | 全 | 受験者最高点 | 101 | 108 | 198 |
| 合格者平均点 | 75.9 | 63.5 | 145.2 | ||
| 受験者平均点 | 72.1 | 57.3 | 134.9 |
| 日程 | 種別 | 国語(120) | 算数(120) | 合計(240) | |
| C日程 | 全 | 受験者最高点 | 96 | 100 | 196 |
| 合格者平均点 | 74.1 | 54.7 | 136.9 | ||
| 受験者平均点 | 68.0 | 46.0 | 122.2 |
換算、合計には、英検加点及び複数受験加点を含みます。
上記以外のものは公表しません。(内部進学⽣のデータは含まれておりません)
過去の入試結果
奈良学園登美ヶ丘中学校
出題形式
令和7年度(2025年度)入試
国語 出題形式・傾向
(120点満点・60分)
1.「字数」が大きな特徴
問題文も、選択肢の文も、記述の指定字数も、とにかく字数が多いのが特徴の一つです。
特に「論説文」では、段落単位で論旨をきちんとつかむことと同時に、文章全体の論旨をつかむことが必要になってきます。
選択肢問題は冷静に、「この選択肢全体で言っていることは正しいか」「選択肢のこの部分は本文内容と合っているか」という視点で読んでいくことで正解にたどり着けます。
2.解答要素の多い記述問題
日程によっては「60~100字程度の記述問題」が出題されます。
そのような長く解答要素の多い記述問題については、「本文のいくつかの部分の内容を結びつける」「自分の言葉で補足する」ことが必要であり、 難易度は高いです。
下記の表は、A日程の出題内容
| 大問1 | 本文内容 | 物語文(有本綾『今日もピアノ・ピアーノ』より) 少年が葛藤を乗り越えて自立心を持ち始める内容 |
| 問1 | 本文の空所補充(慣用表現の空所補充2問・体の一部を表す漢字を書く) | |
| 問2 | 本文の空所補充(適当な擬態語を答える問題2問・選択肢問題) | |
| 問3 | 語句の意味(「対照的」「一触即発」それぞれの意味・選択肢問題) | |
| 問4 | 心情を説明した文の空所補充(2問・選択肢問題+10字以内の記述問題) | |
| 問5 | 心情説明(選択肢問題) | |
| 問6 | 本文中の空所補充(「登場人物の言葉」としてふさわしいもの・選択肢問題) | |
| 問7 | 主人公の心情変化の説明(記述問題80字以内) | |
| 大問2 | 本文内容 | 論説文(鴻上尚史『「空気」と「世間」』より) 電車内での行動を話題としながら日本人の社会観について論じる内容 |
| 問1 | 本文の空所補充(修飾語)(4問・選択肢問題) | |
| 問2 | 本文内容を説明した文の3つの空所の補充 (記述問題・10字以内+15字以内+25字以内) | |
| 問3 | 慣用句の知識(「手を貸します」の「手」の意味・選択肢問題) | |
| 問4 | 本文中の具体例についての説明(選択肢問題) | |
| 問5 | 傍線部の表現効果の説明(選択肢問題) | |
| 問6 | 筆者の見解の説明(記述問題・60字以内) | |
| 大問3 | 問1 | 漢字の読み(4問) |
| 問2 | 漢字の書き(6問) |
奈良学園登美ヶ丘中学校
入試対策ポイント
国語 入試対策
1.時間配分に注意
制限時間に対する「字数(本文・選択肢)」がかなり多いので、時間配分に注意が必要です。
2.「論旨把握意識」を持って論説文を読むことの習慣化
① 長い文章の攻略=段落単位での要旨の読み取り
長文に対しては「慣れ」が必要ですが、むやみに長い文章を読んでも効果は薄いです。
段落単位で、きちんと「要旨」を読み取る「習慣」が重要となってきます。
② 長い選択肢の攻略=選択肢を部分に分けて考える
選択肢問題に対しては、選択肢をいくつかの要素に切り分けて、それぞれの要素と問題文を比べましょう。
「選択肢が、問題文のどの部分に関係しているか?」さえ見つかれば、それほど迷わずに選べるものが多いです。
その点では「要旨を読み取る」という習慣ができている受験生にとっては、それほど難問とはなりません。
3.「自分の言葉」で表現する訓練
記述問題は自分で表現を工夫しなければならないレベルであり、普段から頭で理解したことを言葉で表す習慣を持つことが重要です。
また、問題を解く練習だけでなく、授業中のしっかりした発言を積み重ねていくことで長い記述問題でもきちんと自分の言葉で埋める力が身についていきます。
4.知識領域の反復学習
漢字、語句については難しめの問題が目立つため、日頃から問題演習を欠かさず行うことが重要です。
漢字ガイダンスやSUCCESS・魔法のノート・季節講習テキストの知識ページ、実力テストの勉強など、日々の学習が入試に直結していることを忘れずに取り組むことが合格への道です。
奈良学園登美ヶ丘中学校の合格者の声
京都教育大学附属桃山中学校/奈良学園登美ヶ丘中学校(Ⅱ類) 合格
奈良市立一条高等学校附属中学校/奈良学園登美ヶ丘中学校(Ⅱ類)/育英西中学校(立命館コース) 合格
奈良女子大学附属中等教育学校/奈良学園登美ヶ丘中学校(Ⅱ類) 合格
奈良学園中学校/奈良学園登美ヶ丘中学校 合格
奈良女子大学附属中等教育学校/奈良学園登美ヶ丘中学校/智辯学園中学校 合格
奈良女子大学附属中等教育学校/奈良学園中学校(特進コース)/奈良学園登美ヶ丘中学校(Ⅰ類)/帝塚山学院中学校(ヴェルジェ[エトワール]コース) 合格
その他の中学の入試対策ページを見る
大阪教育大学附属天王寺中学校(大教大天王寺)の入試対策は、下記からご覧いただけます。