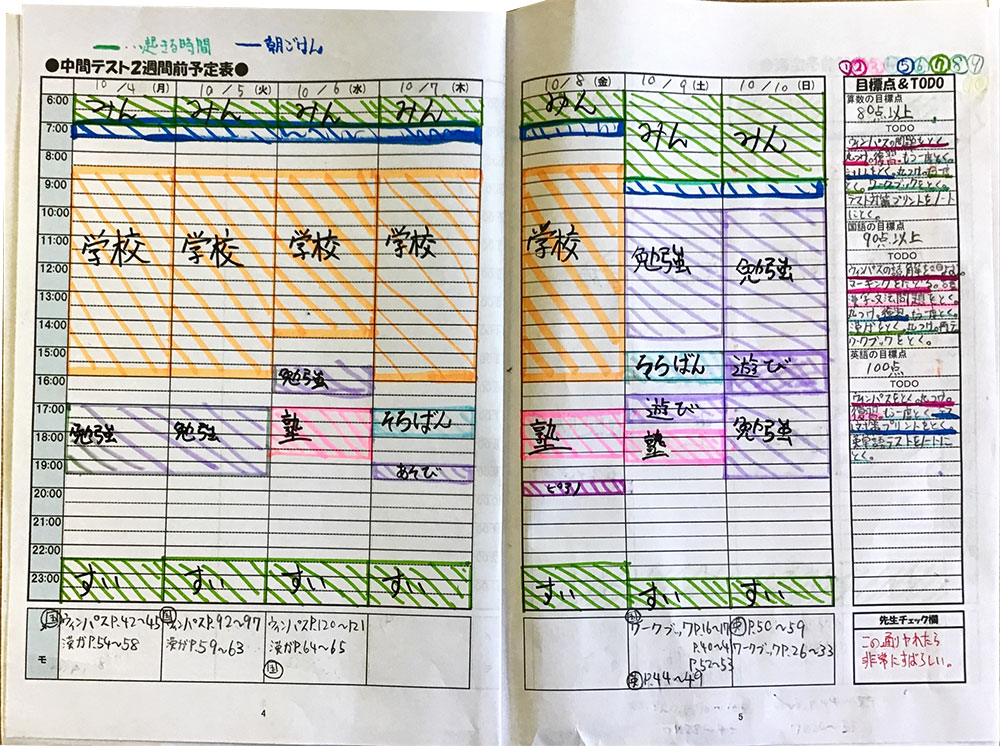青翔中学校の概要
奈良県立青翔中学校は、平成26年(2014年)に開校した学校です。
将来、自然科学の分野で社会に貢献し、日本の未来をリードできる人材の育成をめざす中高一貫教育校。
文部科学省から平成23年度以来、青翔高等学校がスーパーサイエンスハイスクールの指定を受けるなど、充実した理数教育が特徴です。
校風
中高6年間を通じて計画的に探究的な学びを推進するとともに、将来、グローバルな社会で活躍するために、理数科目を中心に幅広く学習したり、英会話や統計、プログラミング等の実用的なスキルを身に付けたりする授業も実施している学校です。
教育方針
法に定められた根本精神と、本県学校教育の指導方針に基づき、豊かな人間性や 社会性を培うとともに、科学的な思考力と創造性を身に付け、科学技術の発展と進歩に寄与する、 心身ともに健全な人間の育成をめざし、指導しています。
お問い合わせ先
TEL:0745-62-3951
所在地
〒639-2200
奈良県御所市525
青翔中学校の入試情報
入試情報
青翔中学校の入試対策の特徴
青翔中学校の入学適性検査は、適性検査1、2、3で実施されます。
青翔中学校
令和7年度(2025年度)入試結果について
定員・倍率・合格者平均点
青翔中学校の令和7年度(2025年度)の入試結果は、101名が受検し80名が合格。
実質競争倍率1.26倍となりました。
合格者の平均点は、280点満点中183.1点となりました。
| 募集人員 | 受検者 | 合格者 | 倍率 | 合格者平均点 |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 101 | 80 | 1.26 | 183.1点/280点満点 |
過去の入試結果
青翔中学校
入学者の選抜方法について
青翔中学校では、
- 適性検査1「言語や社会に関する内容」(40分間)/100点満点
- 適性検査2(50分間)「自然や数理に関する内容」/150点満点
- 適性検査3「テーマの内容を聴き取り、要約し、グループ内で自分の考えや意見を発表」/30点満点
の3つの適性検査が実施されます。
青翔中学校
令和7年度(2025年度)出題形式
適性検査1:国語
1.「理系」色の文章における論理的読解・作文が試される
傾向は変わらず、「理系」色が強い内容の文章を素材とし、設問は「本文内容を『正確に』読み取れているか」を求めるものでした。
作文についても、①過去には「実験」「観察」「図表の内容の文章化」「進化についての考察」が出題されている、②2025年度は「科学技術と自然」が出題された、というように、「理系」色が強い出題が多いです。
2025年度の作文問題については、「社会科」「SDGs教育」などでも触れる内容ではありますが、過去からの出題傾向からは、「理系」としての出題と見るべきでしょう。
なお、「科学技術の発達によって失われる自然」という本文内容を踏まえて、作文の解答は「科学技術との関連」で書くことが妥当です。
2.知識問題・作文問題の重要性
「知識系」といえる設問は2題ですが、作文以外の設問数が7題であることを考えると、知識系で確実に得点することが重要となります。
作文については、過去には「キリンの首が長い理由(正解の範囲が限定的)」などのように「正解とみなされる内容が限定的な作文(『この内容なら正解(不正解)』が明確な作文)」の出題や、2025年度の「一定の観点(=科学技術の発達)に関連させて書く」という出題など、一定の「正解の範囲」があり、受験生間での点差がつきやすい出題です。
国語領域の問題は大問2
(適性検査1 100点満点(40分) / 国語領域50点・社会領域50点)
| 本文 内容 | 論説文(稲垣栄洋『雑草と日本人』より) 欧米と日本の自然環境・自然観を対比しつつ、「科学技術の発達と自然の関係」 「日本人の自然に対する姿勢の問題点」を指摘する内容 |
|---|---|
| (一) | 二字熟語の組み立て(「発生」と同じ構成の熟語を選ぶ選択肢問題) |
| (二) | 慣用句(「水が豊富である」という観点から成立した慣用句を選ぶ選択肢問題) |
| (三) | 本文中の空所補充(自然と人間の関係を表す表現を見つける書き抜き問題) |
| (四) | 本文中の空所補充(適切な接続語を選ぶ選択肢問題) |
| (五) | 傍線部の説明(傍線部の原因として不適切なものを選ぶ選択肢問題) |
| (六) | 本文内容を説明した文の空所補充(2箇所・書き抜き問題) |
| (七) | 論旨把握(筆者の主張として適切なものを選ぶ選択肢問題) |
| (八) | 作文:日本の自然についての作文 |
青翔中学校
入試対策ポイント
適性検査1:国語 入試対策
1.「要約」「物の見方のストック」「自分の考えの構築」の習慣化
「今読んだ文章」と「過去に読んだ文章」の内容を自分の頭の中で比較する習慣が、「入試会場で『複数情報』を処理する力」につながります。
具体的には、日々の「論理的文章での学習」において下記の①~③を心がけましょう。
① 「『文章の主題』は〇〇、『筆者の主張』は△△、『主張の根拠・理由』は◇◇」というように、文章内容を自分の言葉で説明しましょう。
② 「今読んだ文章」に関連する「過去に読んだ文章」の内容を自分の中で再現しましょう(再現方法は上記①)。
③ その上で、「自分自身の意見の構築」を試みましょう。
2.「知識領域」の反復学習
知識問題については「ローマ字知識」「漢字知識」など、「小学校で学ぶ知識領域全体」が出題範囲となるため、幅広い学習が必要です。
KECの青翔中学校
対策講座・模試情報
●「通常授業」:小5生から、表現国語・表現算数の授業を行い、表現力を高めます。
●「日曜スクール」:小5生・小6生を対象に、出題されやすい問題演習を通して、国算理社の解答力を高めます。
●「奈良女子大附中模試」:小4生・小5生・小6生を対象に、学年相当の問題に決められた時間内で取り組む経験と、解説授業の受講を通して、実戦力を高めます。
また、模擬試験受験後に返却される成績表は、小5・小6生を対象に青翔中学校の判定を出します。その後の学習方針を定めるために、役立てることができます。
KECの合格メソッドについて詳しくみる
こちらをご覧ください。
青翔中学校の合格者の声
奈良県立青翔中学校/智辯学園奈良カレッジ 合格
奈良県立青翔中学校 合格
奈良県立青翔中学校/智辯学園中学校 合格
奈良県立青翔中学校 /奈良教育大学附属中学校 合格
奈良県立青翔中学校 合格
奈良県立青翔中学校 合格
その他の中学の入試対策ページを見る
大阪教育大学附属天王寺中学校(大教大天王寺)の入試対策は、下記からご覧いただけます。