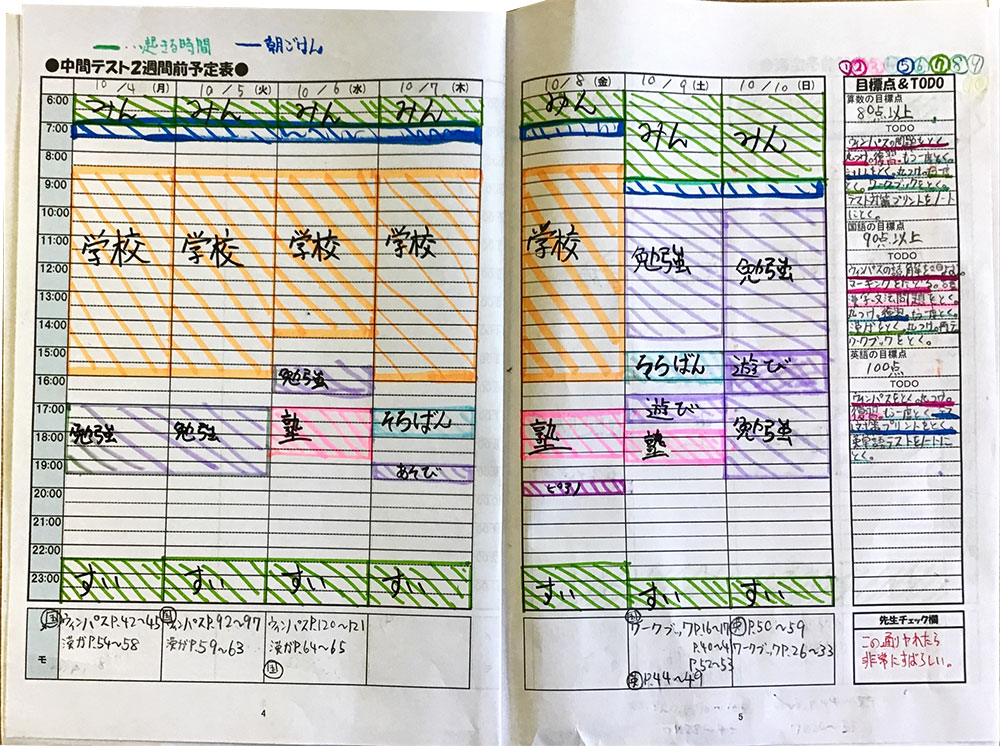一条高等学校附属中学校(2025年度)の入試情報
入試情報
一条高等学校附属中学校の入試対策の特徴
奈良市立一条高等学校附属中学校の入学適性検査は、検査Ⅰ・検査Ⅱに分けて実施されます。
- 検査Ⅰでは、文章や資料を読み解き、課題を整理して適切に表現する力や自らの考えを事実にもとづいて表現する力を測られます。
- 検査Ⅱでは、身近な自然現象やグラフ、図、データ等を分析し考察する力や課題解決に向けて論理的に思考・判断し表現する力を測られます。
上記の入学適性検査の対策として、KECでは、「表現力」を養う専門授業を正課授業として開講しています。
『表現国語』『表現算数』の授業では、下記の3つの力を養うことで「表現力」を育成。
「ディベート・ディスカッション」「作文・記述」など新しい中学入試問題への対応力を鍛えます。
- 「読解力」文章問題をきちんと理解し正確に読み解く力。
- 「伝達力」自分の考えを文章や式で的確に表現する力。
- 「現場思考力」質問や反論に対して瞬時に解答を導く力。
さらに上記の正課授業に加え、市立一条高等学校附属中学校合格を目的とした専門の対策講座を開講しております。
論理的に説明させる記述形式での入試に対応しています。
一条高等学校附属中学校
令和7年度(2025年度)入試結果について
定員と倍率
令和7年度は、80名の募集人数に対して、約2.53倍の202名が受検しました。
| 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実施競争倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 230 | 202 | 80 | 2.53 |
合格者平均点
入学者の選抜は、初年度とおなじく「国語・社会領域」にあたる適性検査Ⅰ・「算数・理科領域」にあたる適性検査Ⅱ、面接、小学校の調査書で行われました。
250点満点のところ、合格者の平均点は179.0点となりました。
過去の入試結果
一条高等学校附属中学校
入学者の選抜方法について
■適性検査Ⅰ
文章や資料を読み解き、課題を整理して適切に表現する力や、自らの考えを事実に基づいて表現する力を測るものです。
■適性検査Ⅱ
身近な自然現象やグラフ、図、データ等を分析し考察する力や、課題解決に向けて論理的に思考・判断し表現する力を測るものです。
■面接
入学や学校生活への意欲と適性等を判定されるものです。
一条高等学校附属中学校
令和7年度(2025年度)出題形式
適性検査Ⅰ(国語領域)出題形式
「適性検査Ⅰ」全体として、2024年度と同じく「大問3問構成(大問1:国語/大問2:社会/大問3:国語・社会融合問題)」でした。
また、「検査Ⅰ全体のボリューム」「国語と社会の設問比率」ともに、2024年度と大きく変わっていません。
1.本文内容を「細かいところまで」「正確に」読み取る力が求められる
設問数は2024年度からの大きな変化はありませんが、下記のような出題があり、高得点を取るためには「本文内容の正確な読み取り」が必要です。
大問1・問四:傍線部を含む段落にも「解答の材料らしきもの」はありましたが、「正しい材料」は違う段落にありました。
かつ、指定字数に合わせて「材料の言い換え」が必要でした。
大問3・問一:「こういうこと」という指示語の指示内容を選ぶ問題でしたが、傍線部の「前の内容」「後の内容」の関係を理解し、「指示内容は傍線部の(前ではなく)後ろである」と判断することが必要でした。
2.「知識系」設問の出題なし
「知識系」の問題については、2022年度は「部首名」「画数」、2023年度は「三字熟語の組み立て」が出題されましたが、2024・2025年度は出題がありませんでした。
3.作文問題は「定型化」傾向
4年連続「空所補充をして題名を決める」「第一段落は『経験』を書く」「第二段落は『考え』を書く」「120字以上150字以内」という出題でした。
ただし、2025年度は初めて「筆者の考えに沿った内容で書く」という条件がつけられました。
これによって「本文内容の理解」「本文内容にあった題名・経験の設定」という、過去3年よりも高度な思考が必要となりました。
国語領域は大問1と大問3の問一・三(適性検査Ⅰ 100点満点・45分)
| 大問番号 | 小問数 | 内容 |
| 1 | 7 | 論説文(「さくらさんが『自己肯定感』の在り方について考えるために読んだ」という設定で、文章を提示) 文章:毛内拡『「気の持ちよう」の脳科学』より 内容:自己肯定感の本質について論じるとともに、「自己効力感」の重要性を説く内容 |
| 問一 漢字の書きとり問題(2問) | ||
| 問二 本文中の二か所の空所に入る接続語の組み合わせ(選択肢問題) | ||
| 問三 傍線部に関して筆者が述べていることの把握(選択肢問題) | ||
| 問四 傍線部に関して筆者が述べていることの把握(記述問題・40字以上50字以内) | ||
| 問五 本文内容を整理した図の空欄補充(2問・選択肢問題) | ||
| 問六 作文問題 「自分は( A )ができる。それは、( B )のおかげだ。」という題名(空所は自分で考える)の作文 ・筆者の考えに沿った内容で書く ・第一段落は題名に関する経験を書き、第二段落は第一段落に書いた内容をふまえての考えを書く ・120字以上150字以内 | ||
| 3 | 2 | 論説文(「はじめさんが『地域』の特徴を考えるために読んだ」という設定で、文章を提示) 文章:山下祐介『地域学をはじめよう』より 内容:社会を「社会有機体(=ひとつの生命体)」としてとらえた上で、「地域」を論じる内容 |
| 問一 指示語が指す内容(選択肢問題) | ||
| 問三 傍線部の言い換え(書き抜き問題) |
一条高等学校附属中学校 入試対策ポイント
適性検査Ⅰ(国語領域) 入試対策
1.一つひとつの動作・学習を「丁寧」に行う
読解問題については、「本文内容の正確な読み取り」が求められます。
また、作文問題では「本文全体の内容の理解」が求められます。
よって、普段の学習では、「文章全体の内容をつかみ自分の言葉で表現してみる(同時に文章を構成している各段落についても同様のトライをする)」「一つひとつの選択肢に対して、『この部分は○』『この部分は×』という書き込みをする」など、「細かく」「丁寧に」解くことを心がけましょう。
2025年度の傾向が続くとすれば、受験までの「習慣」が受験結果に直結することになります。
知識問題については「今後は出題されない」と言える段階ではないので、各分野の学習内容を「受験まで忘れない知識」として身につけましょう。
2.作文は「発想力」「正しく意味が伝わる一文を書く力」を磨く
「150字」「二段落指定」の作文は、「各段落二文程度(全体としては四文程度)」という書き方になります。
文の数が少ないため、「文同士の内容の重複がない」「その一文で確実に『伝えるべきこと』を伝える」ということが必要です。
与えられた「型」に合わせた題名・作文内容を想定できる「発想力」を身につけるために様々な問題に取り組むと同時に、書く際には「一文の重み」を意識して書く習慣を持ちましょう。
※「本文全体の内容の理解」については上記1に記載した通り。
適性検査Ⅱ(算数領域) 入試対策
幅広い単元から出題されるので、まずは基本的な内容を徹底的に押さえておく必要があります。
また、問題を解くのに必要な情報を素早く確認するために、マーキングしながら問題を解く習慣をつけておくことが重要です。後半にも比較的易しい問題が出てくるため、日頃から時間配分を意識しながら問題を解くようにしましょう。
表現算数(適性算数)で学習する内容も出題されているので、算数の内容に限らず、表現算数(適性算数)の内容もきちんと勉強しておく必要があります。
教科書の内容だけでなく、受験算数の基本的な内容をきちんと定着させて入試問題にのぞむようにしましょう。
2025年度は出題されませんでしたが、記述の問題が出る場合もあるので、きちんと対策をしておく必要があります。
KECの一条高等学校附属中学校
対策講座・模試情報
表現講座
「表現力」養成のKECの専門授業です。
この講座では、「表現力」を身につけるために必要な3つの力を養います。
- 本文や複数の資料から示される事実を正確に読み取る「読解力」
- 自分の意見やその理由を的確に伝える「伝達力」
- 質問や反論に対して瞬時に解答を導くことができる「現場思考力」
KECの合格メソッドについて詳しくみる
「これが入試本番に活かされた!」KECの合格メソッドとは?
ぜひこちらをご覧ください。
一条高等学校附属中学校の合格者の声
奈良市立一条高等学校附属中学校 合格
奈良市立一条高等学校附属中学校/奈良学園登美ヶ丘中学校(Ⅱ類)/育英西中学校(立命館コース) 合格
奈良市立一条高等学校附属中学校/奈良学園登美ヶ丘中学校(Ⅱ類) 合格
奈良市立一条高等学校附属中学校/奈良教育大学附属中学校/奈良学園登美ヶ丘中学校(Ⅱ類)/育英西中学校(立命館コース) 合格
奈良市立一条高等学校附属中学校 合格
奈良市立一条高等学校附属中学校/奈良育英中学校 合格
一条高等学校附属中学校の概要
市立一条高等学校附属中学校は、令和4年度開校の奈良市立の中学校です。
中高一貫教育の学びが魅力であり、6年間を通した系統的な学習が可能です。
幅広い異年齢集団で学習し、様々な活動も行い、3年間中学で学んだのち、入学者選抜なしに一条高校へと進学します。
一条高校は、昭和25年に普通科高校として設立され、翌26年には全国初の外国語科(英語)が開設された高校です。
大学進学実績についても、国公立大学や難関私立大学へ多く輩出しています。
校風
奈良市立一条高等学校附属中学校は、Arts STEM教育や高校生との交流もあり、様々な活動を行うことができます。 自分のやりたい事をとことん探求でき、豊かな体験活動から人間性を高めることが可能な学校です。
教育方針
”アクティブシティズンであり、自由に生きることができる「個人」の育成” を掲げており、どんな社会の中でも自立して生きていくことができる人間を育成します。
■ 一条高等学校附属中学校公式HPはこちら
お問い合わせ先
TEL. 0742-33-7075
FAX. 0742-34-8809
所在地
〒630-8001
奈良市法華寺町1351 番地
アクセス方法
交通:近鉄「新大宮」駅から徒歩800m、JR「奈良」駅から徒歩・自転車1900m、近鉄「奈良」駅からバスで10分
その他の中学の入試対策ページを見る
大阪教育大学附属天王寺中学校(大教大天王寺)の入試対策は、下記からご覧いただけます。