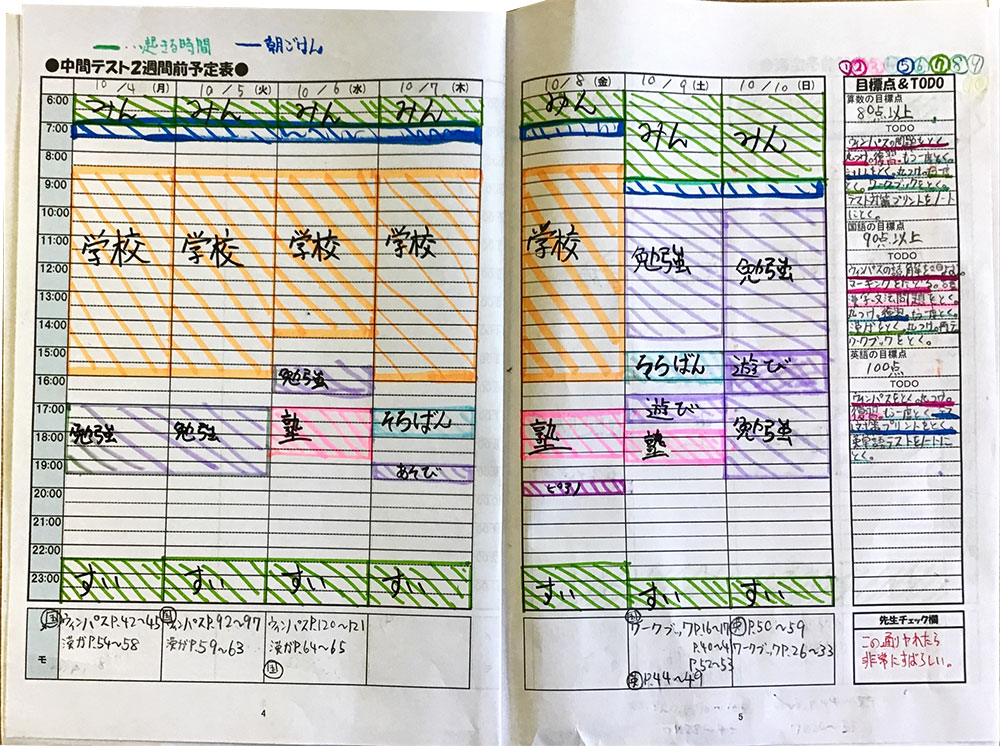KEColumn
小学生の“考える力”を家庭で育てる方法―日常の声かけで柔軟な発想力を伸ばそう!
家庭の声かけで小学生の“考える力”を育てるコツ
お子さまにとって、これから必要になるのは、決まった答えを暗記するだけの学びではなく、自分で考え、工夫し、答えを導く力です。
なぜなら、知識は検索ですぐに手に入る時代となり、社会では「正解のない課題」を解決する力がますます求められているからです。
学校教育や大学入試でも「思考力・表現力」を重視する方向へ変わりつつあり、企業も新入社員に「主体性・協働力・創造性」を強く求めています。
だからこそ、小学校低学年のうちから暗記にとどまらない「自分で考え、答えを導く力」が必要なのです。
その力は特別な教材や難しい問題集だけで育つのではなく、例えば、日常生活の中で保護者さまと交わす何気ない会話や問いかけの積み重ねからも生まれてくるものです。
「どうしてそう思うの?」「ほかにもやり方があるかな?」と声をかけるだけで、お子さまは考えるチャンスを得ることができます。小さな問いかけの積み重ねこそが、将来の大きな伸びしろになります。
では、なぜこうした“柔軟な思考力”が大切なのでしょうか?
なぜ小学生には柔軟な思考力が必要なのか?
決まったやり方だけでは伸びない理由
「やり方を一度覚えたら、それ以外の方法を試そうとしない」
「少し状況が変わると、すぐに手が止まってしまう」
そんなお子さまの様子を見て、心配になったことはありませんか?
小学生のうちは、正解がひとつの問題を解く機会が多いため、どうしても“正しいやり方だけを覚えて、同じパターンで解くクセ”がつきがちです。
でも実際の生活や、これからの社会で求められるのは、与えられた知識をどう活かし、状況に合わせて柔軟に考えるかという力です。この柔軟さは、保護者さまとの何気ない会話や、日常での小さな選択の積み重ねからも育っていきます。
低学年期は“柔らかい発想”が育つ黄金期|家庭での関わり方がカギ
小学校低学年のお子さまは、思考が柔軟で、いろいろな考え方を吸収できる時期です。
この時期に、
- 答えはひとつではないかもしれない
- 別の方法でもできるかも
- 自分で考えてみるのも楽しい
などといった経験を積むことが、将来の大きな伸びにつながります。
反対に、早い段階から「こうやるのが正しい」と決めつけてしまうと、失敗を恐れて挑戦しなくなったり、すぐに諦めたりするクセがつきやすくなります。だからこそ、低学年から自由に考え、試行錯誤する体験がとても大切なのです。
家庭でできる!小学生の考える力を伸ばす声かけ例10選
家庭で考える力を育てるには、少し意識を変えるだけで十分です。
日常生活の中のちょっとした声かけが、柔軟な発想を育むきっかけになります。
✅ 正解を一つに決めつけず発想を広げる問いかけ
1.「これ以外にやり方ってあるかな?」
2.「もし〇〇だったら、どうなると思う?」
3.「これを使って別のことができるとしたら?」
✅ 思考を深める・理由を考える問いかけ
4. 「どちらがいいと思う?どうしてそう思ったの?」
5. 「この順番と逆にしたら、どうなるかな?」
6. 「一番早く終わるやり方はどれだろう?」
✅ 生活の中で“考える場面”をつくる問いかけ
7. 「3人分にするには、分量をどうすればいい?」
料理を一緒にする中で考えてみる
8. 「どの道が早いと思う?天気が悪かったらどうする?」
お出かけ前に一緒に予定を立ててみる
9. 「いつもとは違うルールで遊んでみようか?」
遊びのルールをお子さまと一緒に変えてみる
✅ 失敗を“挑戦の一歩”として肯定する
10. 「うまくいかなかったけど、次はどうすればいいと思う?」
こうした小さな問いかけや会話が、決まったやり方に縛られない柔軟な発想力を育てる土台になります。
さらに考える力を深めたいなら|家庭学習と組み合わせられる学び方
家庭での声かけだけでも十分ですが、さらに体系的に“考える力”を伸ばしたい場合は、学び方を工夫できる教材や習いごとも選択肢のひとつです。
その一例が、KECゼミナール・KEC志学館ゼミナールで開講している玉井式国語的算数教室です。
物語やアニメーションを通して学ぶ体験を通じて、算数の力だけでなく、想像力(イメージング力)・読解力・思考力などを育てることができます。
家庭ではなかなか難しい部分をサポートしながら、お子さまが“考えるって楽しい!”と思えるきっかけになるはずです。
「うちの子にも合うかな?」と思われたら、まずはお気軽に無料体験をお試しください。
体験に、実際に参加すると、お子さまの新しい一面に気づけるかもしれません。

.jpg)
サムネイル.jpg)

サムネイル.jpg)
サムネイル-2.jpg)