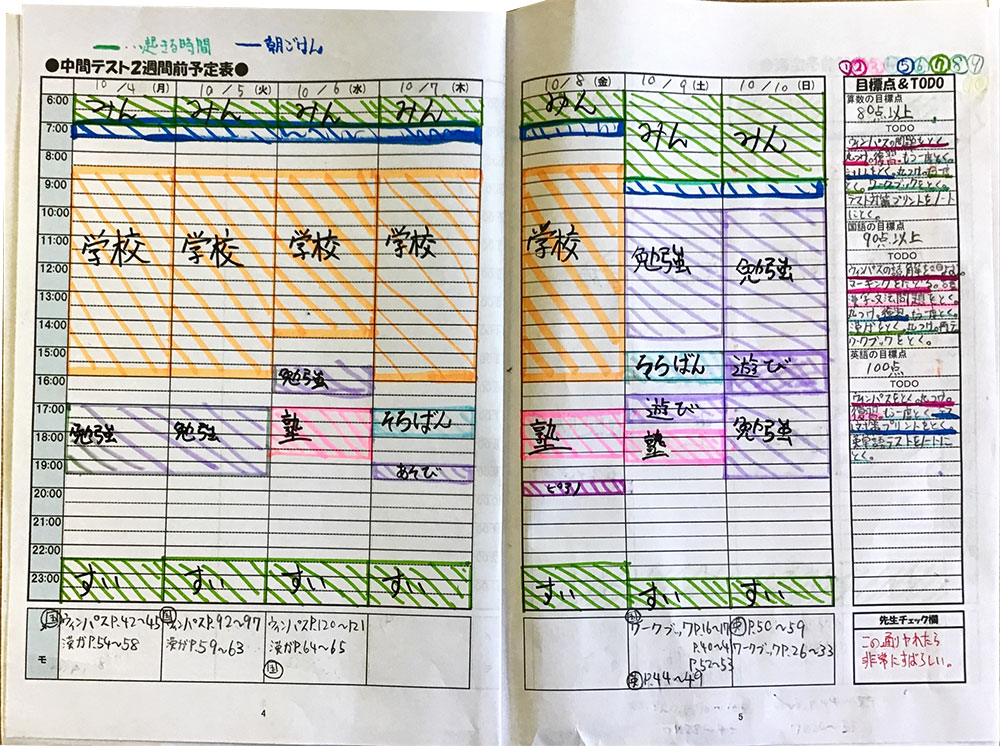KEColumn
2学期に成績が下がる理由と対策法!学習ペースを保つ秘訣
1学期は順調だったのに…2学期で失速する原因は?
夏休み明けは気持ちを新たにスタートできる一方で、お子さまの様子を見て「宿題に取りかかるのが遅いな」「少し疲れているかな」と感じることはありませんか?
2学期は、1学期に比べ勉強の難しさも増し、生活リズムも乱れやすい時期です。そのため「このまま成績が下がってしまうのでは」と心配になる保護者さまもいらっしゃいます。実際にはまだ成績に表れていなくても、今のうちから気をつけておくことで“下がる前に”備えることができます。
では、なぜ2学期は“失速”が起こりやすいのでしょうか。
夏の“貯金”と“疲れ”の両面から見る学習ペースの落とし穴
夏休みはまとまった時間があるため、復習や苦手克服に取り組める大切な期間です。
その努力は確かに「学習の貯金」となります。しかし同時に、生活リズムの乱れや遊びでの疲れがたまりやすい時期でもあります。さらに2学期は運動会や校外学習など学校行事が増え、学習内容も1学期より難易度が上がっていくため、“心身の疲れ”と“学習の負担”が重なるのです。結果として、せっかくの夏の学習の成果がうまく発揮できず、テストや授業で「失速」したように見えてしまいます。
例えば、小学校5年生のあるお子さまは夏休みに計算練習をしっかり行い、最初のテストでは高得点を取ることができました。しかし、2学期の途中から宿題に取りかかる時間が遅くなり、就寝も遅れるように…。次第に授業中の集中力が続かなくなり、テストの点数が下がってしまったのです。学力不足と見えがちな点数の低下も、実は生活リズムの乱れが引き起こしているケースもあります。
こうしたケースは「気づいたら下がっていた」というよりも、必ず小さなサインから始まります。例えば、宿題の開始時間が遅くなる、忘れ物が増える、集中が途切れやすくなるなどです。まだ成績に表れていなくても、この段階で工夫を始めれば“下がる前に”学習ペースを立て直すことができます。
.jpg)
継続できる子の特徴と習慣—環境と声かけがカギ
成績を安定させられるお子さまは、日々の学習リズムが身についています。例として、『宿題は夕食前に終える』『1日10分だけ漢字や計算の復習をする』など、無理なく続けられる小さな習慣があると、ペースを崩しにくくなります。こうした習慣づくりは、単に生活を規則正しくするだけでなく、2学期から難しくなる学習内容に立ち向かうための「土台」となります。さらに、『ここまでできたね』『昨日より早く取りかかれたね』と保護者さまからお子さまへ成果を認める声かけが、学習への前向きな気持ちを支えます。
KECゼミナール・KEC志学館ゼミナールでも、こうした“集中して学習習慣を積み重ねる工夫”や“できたことに注目する姿勢”を大切にしています。これは家庭でも同じように取り入れられる考え方です。生活の流れの中に学習を自然に組み込むことが、結果として成績の安定につながりますし、下がる前に備える有効な方法にもなります。
また、こうした習慣づくりは小学生のうちに身につけておくことが大切です。中学校に進学すると科目数が増え、学習内容もさらに難しくなり、部活動との両立も必要になります。そのときに小学生のうちから「学習のリズム」を確立している子は、ペースを崩しにくく、大きなつまずきを防ぎやすいのです。逆に、小学生のうちに習慣が身についていないと、中学校での急な変化に対応しづらくなります。だからこそ、“今”が習慣づくりのチャンスといえます。
今こそ、立て直しとリズムづくりを
2学期は“夏の疲れ”と“内容の難化”が重なるため、どうしても成績が下がりやすい時期です。だからこそ、今のうちに学習リズムを整え、保護者さまからのちょっとした声かけで、前向きな気持ちを引き出すことが大切です。小学生のうちから習慣を整えておけば、中学進学後の安定した学習にもつながります。保護者さまの見守りと応援が、お子さまにとって大きな支えになります。
.jpg)
学習習慣づくりをサポートします
「家庭での学習ペースづくりが難しい」「学習習慣を身につけるために塾を探している」という保護者さまは、ぜひ一度無料体験に参加してみませんか。
KECゼミナール・KEC志学館ゼミナールの公立中学進学プライムコースでは、授業や宿題、プライム定期テストを通して学習習慣を定着させる工夫をしています。集団で学ぶ中でも「やればできる」という経験を積み重ねることで、お子さまは前向きに学び続ける力を養うことができます。2学期を自信を持って乗り越えるヒントを、ぜひ体験の中で見つけてみてください。

.jpg)
サムネイル.jpg)

サムネイル.jpg)
サムネイル-2.jpg)