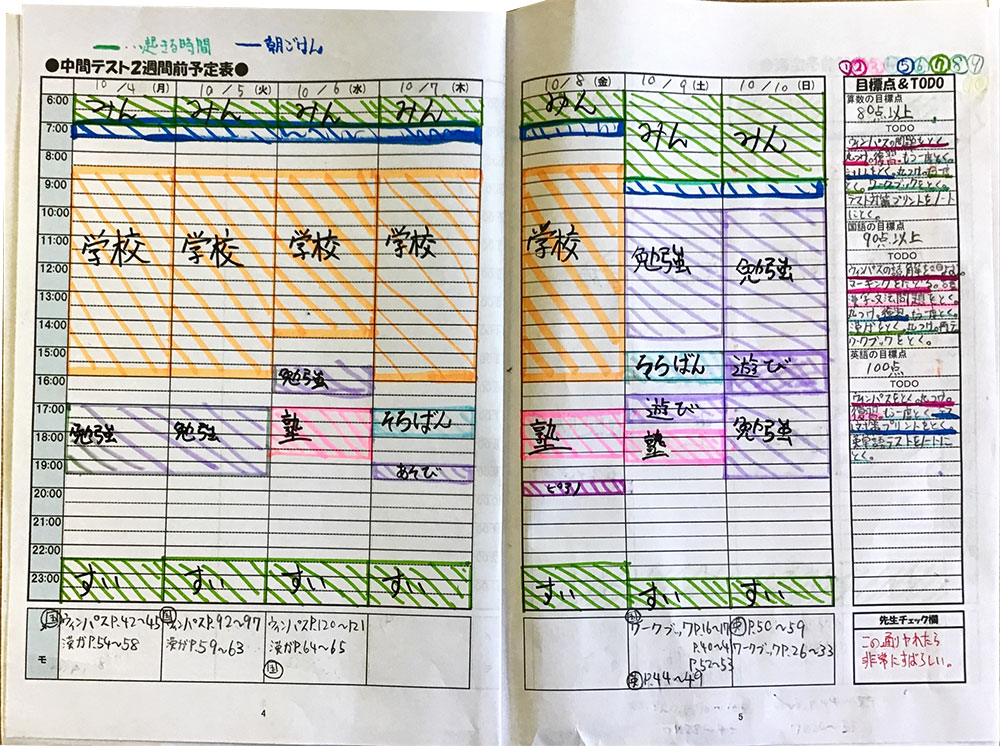KEColumn
小学生の算数が苦手な理由は“読解力”?文章題に強くなる家庭学習法
なぜ「読む力」が算数に必要なのか
「計算はできるのに、文章題になると手が止まってしまう…」
そんなお子さまの姿を見て、心配になったことはありませんか?
「足し算や引き算は覚えているはずなのに、なぜ?」と思われる保護者さまも多いのではないでしょうか。
実はその“つまずき”の背景には、計算力そのものではなく、「読む力=読解力」が関係しているケースがよくあるのです。
算数というと「数字」が中心の教科と思われがちですが、実際の学びの中では、場面を読み取り、条件を理解し、自分で式を立てるという“読んで考える力”が必要不可欠です。
つまり、「国語が苦手だから算数も苦手に感じてしまう」というお子さまも、少なくないのです。
文章題に求められる“読解力”とは
算数の文章題には、ただ「読む力」ではなく、“意味を理解して状況を整理する力(=イメージング力)”が求められます。
たとえば「りんごが5こあります。3こ食べました。のこりはいくつですか?」という文章題。
これを正しく解くには、次のような思考のステップが必要です。
- 「りんごが5こある」という状況をイメージする
- 「3こ食べた」という出来事が何を意味するのかを理解する(数が減ること)
- 「のこりはいくつか?」という問いに対応する式を立てる(5-3=2)
このように、単に文字を追うだけではなく、場面を頭の中で整理し、数の変化を捉える力が必要なのです。
低学年のうちは、これらの力がまだ発展途上のため、文章題が「難しい」「よくわからない」と感じてしまうのは自然なことなのです。
修正-1024x683.jpg)
“読解力”を育てるには?
では、どうすればお子さまの「読む力」を育て、算数の文章題に強くなれるのでしょうか。
まず大切なのは、普段から「ことばに触れる経験」を増やし、豊かにすることです。
「ことばに触れる経験」から育まれる力
普段の生活の中でことばに多く触れることによって、次のような力が育っていきます。
- 語彙が増える → 理解の幅が広がる!
- 表現に慣れる → 文の構造がつかめる!
- 背景知識が増える → 推測力が育つ!
- 感性が育つ → 深く読む力につながる!
- 書く力にもつながる → アウトプットが強くなる!
たとえば、絵本の読み聞かせや、算数の文章題を「読み物」として言葉にして話すなど、親子で日常を一緒に楽しむ工夫も効果的です。
「今日はどんなことがあった?」「どうしてそう思ったの?」と問いかけて、言葉で表現する練習を一緒にしてみてください。
計算だけでなく、意味を読み取る力を低学年から育てよう
低学年のうちは、「計算ドリルを解くこと」も必要ですが、イメージしながら「意味を理解する力」を育てることが、のちの学力の土台になります。
文章題に強くなるには、国語力や生活経験がつながっていることを意識して、焦らずゆっくりと“考える力”を育てていきましょう。
家庭での会話や読み聞かせ、そして「わかる!たのしい!」という体験の積み重ねが、お子さまの学びを支えてくれます。
\日常の声かけで、学びをもっと楽しく/
KECゼミナール・KEC志学館ゼミナールでは、学習における土台「イメージング力」を育てるために、「玉井式国語的算数教室」を開講しています。
アニメーションと物語を通じて、楽しみながら文章題に取り組めるのが特長です。
低学年のお子さまにとっては、「往復」や「おつり」など、大人にとっては当たり前に日常で使う言葉でも、実はお子さまが理解していない言葉が文章題に出てくると、意味がわからずつまずいてしまうことがあります。
講座では、そうした言葉や場面設定を丁寧に説明してから問題に取り組むため、「なんとなく読む」のではなく、しっかり理解して考える習慣が自然と身についていき、「算数の文章題がわかるようになったのと同時に国語の力もついた!」というお声もいただいています。
修正-1024x683.jpg)
KECゼミナール・KEC志学館ゼミナールの「玉井式国語的算数教室」では、無料体験授業も実施中です。
まずはお気軽に、教室の雰囲気を体感してみてください。

.jpg)
サムネイル.jpg)

サムネイル.jpg)
サムネイル-2.jpg)