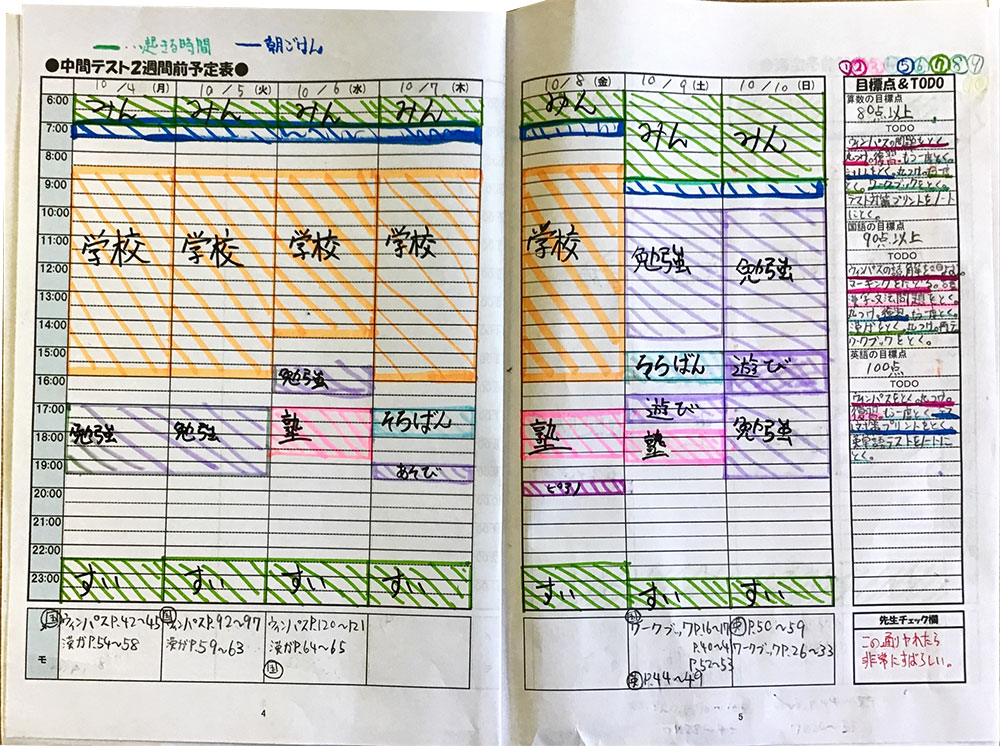奈良教育大学附属中学校 令和7年度(2025年度)の出題形式について
奈良教育大学附属中学校 令和7年度(2025年度)出題形式
国語
1.内容は変化なし・難易度は「やや易化」/「『知識領域』・『問われ方』への対応力」が求められる
「問題数」「小問の内容」などは2023・2024年度の入試と同様でした。
ただ、作文の指定字数が180~200字(過去2か年は240~300字)と減少したことから、試験全体のボリュームという点では「やや易化」したといえます。
知識領域については、2024年度が「敬語」「熟語の構成」、2025年度は「助動詞・助詞」「ことわざ・慣用句」が出題され、「知識分野全体から何かを出題する」という方針であると考えられます。
読解問題については、(4)~(10)のように「論旨把握を試す設問」という共通点はありながらも「質問の仕方(問い方)」に変化を持たせています。
2.作文問題のテーマは年度によって異なる
2023年度:マスクをしてのコミュニケーションの問題点+コミュニケーションで大切だと思うこと
2024年度:おすすめの本について、その本の紹介+どのような人に(どのようなときに)読むことをすすめるか
2025年度:言葉の力を感じた出来事の状況説明+その経験を生かしたいことや、その経験からの学び
作文問題が復活してから3年になりますが、上記のように「作文のテーマ」は変化しつづけています。
2026年度以降も「様々な出題」に対する対応力が試されると考えられます。
30点満点(40分)
| 大問1 | (1) | 漢字書き取り(2問) |
| (2) | 漢字の読み(2問) | |
| (3) | 主語を選ぶ問題(選択肢問題・3問) | |
| (4) | 四字熟語(四字熟語に当てはまる状況を答える選択肢問題・3問) | |
| 大問2 | 本文内容 | 論説文(鷲田清一『わかりやすさはわかりにくい?――臨床哲学講座』より) 内容:「他者の理解」「ほんとうのコミュニケーション」とはどのようなものかを指摘する内容 |
| (1) | 接続語の補充(選択肢問題・3問) | |
| (2) | 脱文補充(設問で提示された文章が本文中のどこに入るかを答える・選択肢問題) | |
| (3) | 同内容表現(傍線部と同内容の表現を本文中から探す・書き抜き問題) | |
| (4) | 論旨把握(傍線部に対しての筆者が感じていることを答える・書き抜き問題) | |
| (5) | 論旨把握(傍線部の原因や指示語内容をおさえる・書き抜き問題) | |
| (6) | 同内容表現(傍線部と同じ意味で用いられている表現を本文中から探す・書き抜き問題) | |
| (7) | 論旨把握(傍線部の原因をおさえる・書き抜き問題) | |
| (8) | 論旨把握(傍線部に対しての筆者の考えとして適切なものを選ぶ・選択肢問題) | |
| (9) | 論旨把握(傍線部の説明として適切なものを選ぶ・選択肢問題) | |
| (10) | 論旨把握(筆者が述べていないことを選ぶ・選択肢問題) | |
| 大問3 | 作文 | 「言葉の力を感じた出来事」という題名で作文する。 ・二段落で書く 第一段落は「言葉の力を感じた出来事」と「そのときの状況」を書く。 第二段落は「その経験を生かしたいこと」あるいは「その経験から学んだこと」を書く。 ・180字以上200字以内 |
算数
2020年度から大問数はずっと6問でしたが、2025年度は大問数が7問に変わりました。
小問数も2024年度は20問でしたが、2025年度は24問に増えました。
そのため、受験生の中には時間配分が上手くいかず、最後まで解ききれなかった人もいた可能性があります。
毎年、図形の作図の問題やさまざまなグラフの作図の問題が出されています。
2025年度は、コンパスを用いた図形の作図が出題されました。
2021年度 正三角形の作図、棒グラフの作図
2022年度 棒グラフの作図、速さとグラフの作図
2023年度 2量の関係を表すグラフの作図
2024年度 問題の考え方を説明するための図形の作図、図形の移動とグラフの作図
2025年度 糸が動いたあとの作図
図形の問題は毎年レベルの高い問題も多く出されていましたが、例年と比べると比較的簡単な問題が多かったです。
よって、解ける問題を確実に正解することが、 合格ラインを超えるうえで、非常に重要なポイントになったと思われます。
30点満点(40分)
| 大問番号 | 小問数 | 内容 |
|---|---|---|
| [1] | 5 | 計算問題 |
| [2] | 5 | 小問集合 |
| [3] | 3 | 倍数と場合の数 |
| [4] | 2 | 点の移動とグラフ |
| [5] | 2 | 資料の調べ方 |
| [6] | 3 | (1)図形の移動(作図の問題あり)(2)拡大図と縮図 |
| [7] | 4 | 容積 |
総合:理科
2025年度も、2024年度同様大問が6問ありました。
また、小問が14問(うち記述問題1問)となり、2024年度同様の問題数でした。
2024年度の記述問題は、資料をもとに考える問題でしたが、2025年度は時事からの出題になったため、知らない生徒にとっては考えづらい問題になりました。
また、実験の図、実験結果、資料などからの出題も多く、「普段から、資料から読み取れることを考える習慣が大切になってきます。」
また2025年度は、大問1の(3)や、大問3(2)のような、問題文や図をていねいに整理しないと難しい問題もふくまれており、普段からていねいに問題文を読む習慣が必要になってきます。
総合(理科と社会に分かれる)で60分、30点満点。
理科領域:大問6問、 小問14問。理科にかけられる時間は30分程度で15点満点。
| 大問番号 | 小問数 | 内容 |
|---|---|---|
| [1] | 3 | (1)メスシリンダーで100mLはかり取った水を200mLのビーカーに移したとき、水の重さと体積はどのように変化するかを 選ぶ問題 (2)水をこおらせたときの重さと体積の変化を選ぶ問題 (3)上皿てんびんで氷の重さをはかった結果から、氷の重さが何gより重く、何gより軽いかを答える問題 |
| [2] | 3 | (1)1日の気温の変化のグラフから晴れの日を選ぶ問題 (2)アブラナの花のさく時期を選ぶ問題 (3)「月は東に 日は西に」という句から、月の形を選ぶ問題 |
| [3] | 2 | (1)片方の肩からひじまでの腕の骨の本数と、ひじから手首までの腕の骨の本数の組み合わせを選ぶ問題 (2)厚紙で作った「肩からひじまでの腕の骨」「ひじから手首までの腕の骨」「手」の模型に、ひじを曲げ伸ばしするための ゴムをどこに着けるか選ぶ問題 |
| [4] | 1 | 鉄板を4枚重ね、一方を輪ゴムでとめた装置を磁石に近づけたとき、どのようにくっつくかを選ぶ問題 |
| [5] | 4 | (1)ふりこの長さは、どこからどこまでかを選ぶ問題 (2)おもりの重さを重くしたり、ふりこの長さを長くしたとき、ふりこが10往復してもとの位置に戻るまでにかかる時間が どのように変化するかをそれぞれ選ぶ問題 (3)ふりこのおもりが最も速く動くふりこを選ぶ問題 (4)実験結果から、長さ80cmのふりこの支点の真下40cmに棒を固定して、途中から長さの変わるふりこが 10往復する時間を計算で求める問題 |
| [6] | 1 | 段ボールベッドを使うことで抑えられると考えられる環境への影響について、具体的な例をあげて意見を書く問題 |
総合:社会
大問1は日本の国土や沖縄、情報に関する「地理分野」と、近世・近現代に関する「歴史分野」、選挙や国際連合に関する「公民分野」の融合問題です。
学校の教科書に記載されている内容を基本としていますが、資料の分析力も必要となります。
また、選択問題については「正しいもの」「まちがっているもの」を選択する形式が混在するので、マーキングを行うなどしてミスを防ぐことが必要です。
大問2は資料から読み取れる内容をまとめる問題と、課題を思考し、その課題を解決するための意見をまとめるという2つの記述問題が出題されました。
総合(理科と社会に分かれる)で60分、30点満点。
大問2問、小問11問。社会にかけられる時間は30分程度で15点満点。
| 大問番号 | 小問数 | 出題内容 |
|---|---|---|
| [1] | 8 | (1)マスメディアと私たちの関わりについて、まちがっている文を1つ選択する問題 (2)那覇市を示した雨温図を1つ選択する問題 (3)沖縄について正しく説明した文を2つ選択する問題 (4)森林について説明した文について、まちがっているものを1つ選択する問題 (5)織田信長について説明した文について、まちがっているものを1つ選択する問題 (6)明治時代と昭和時代に関する選択肢を古い順にならべかえる問題 (7)4つの資料を読み取り、日本の選挙に関する文について、まちがっているものを1つ選択する問題 (8)国際連合について説明した文について、まちがっているものを1つ選択する問題 |
| [2] | 3 | (1)核兵器の被害を伝え、世界平和を訴えるシンボルとして、世界文化遺産に登録された建物の名前を答える問題 (2)世界の子供たちに起きている問題と、その解決のためにユニセフが行っている活動を資料から読み取り、 60字以上100字以下で説明する問題 (3)人々の平和と友愛のために大切なことと、その実現のために自分自身ができることを80字以上140字以下で 説明する問題 |
面接
1グループ4~5名(男女混合)での実施。(10点満点・10分間程度)
| 内容 | |
|---|---|
| グループディスカッション | 国際化が進む中、英語を公用語として日本語を制限するという考えについて、話し合いなさい。 ※条件:司会を決めること/一人1回以上発言すること |