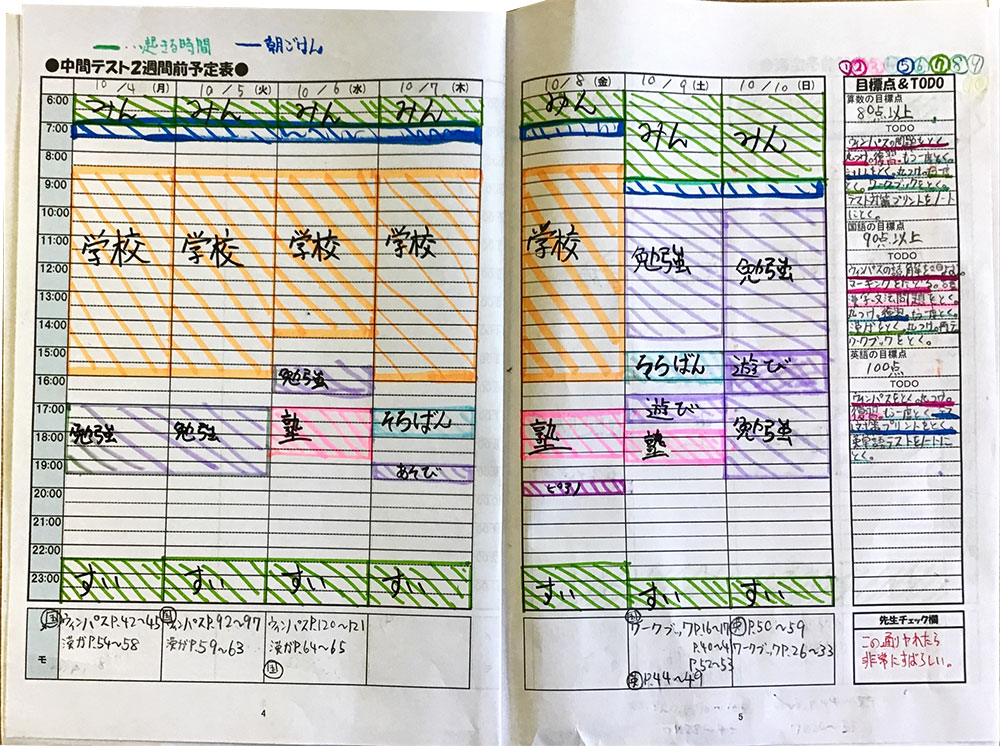京都教育大学附属桃山中学校 令和7年度(2025年度)の出題傾向/出題形式について
京都教育大学附属桃山中学校
出題傾向/出題形式
国語
(40点満点・40分)
1.「物語文」「論説文」「作文」の3本柱
構成については直近6年で変更なく「物語文+論説文+作文」です。
「詩」「短歌・俳句」の出題例はありません。
2.設問数が多く、「時間配分」が大きな鍵となる
試験時間40分に対し、 22問の小問(そのうち6問が記述問題)と1問の作文問題であるため、「時間配分」のハードルがかなり高くなっています。
時間内に全問を解き切る対策が必須となります。
3.1問あたりの配点が小さい
小問22題・作文1題で40点満点であることから、「1問あたりの配点は小さい」と考えられます。
ただし、作文については指定される字数の多さから考えて、「ある程度高い配点」であると考えられます。
よって、作文以外の設問を「ポイントを押さえてスピーディーに」解き、作文問題を書く時間を確保することが重要です。
「試験時間内に作文まで書き切れるかどうかが合否を左右する」と言っても過言ではありません。
4.作文は「自己語り」という出題が続いている
2023年度は「あなたは何のために働きたいか? どのような仕事をしたいか?」、2024年度は「あなたは、どうするか?」を問う作文であり、過去2年間は「未来を語る作文」であったが、2025年度は「過去を語る作文」でした。
また、2022年度まで続いた「~した体験と、その体験に基づく考え(学び)を書く」という指示とは異なり、「経験を書く」のみの指示でした。
これまでの出題を総括すると「自分について書くという『軸』を保ちつつ、バリエーションをつける出題」といえます。
| 大問1 | 本文内容 | 物語(天沢夏月『青の刀匠』より) 刀鍛冶を通して少年が成長する物語の一場面 |
| 問1 | 漢字の読み書き(書き1問・読み1問) | |
| 問2 | 熟語の成り立ち(「水深」と成り立ちが同じ熟語・選択肢問題) | |
| 問3 | 本文中の「川」の説明(選択肢問題 ※あてはまらないものを選ぶ) | |
| 問4 | 修飾・被修飾の関係(「そんな」がかかる部分・選択肢問題) | |
| 問5 | 会話文(セリフ)の内容の具体化(記述問題・30字以内) | |
| 問6 | 会話文の内容の具体化(記述問題・35字以内) | |
| 問7 | 会話文の内容の具体化(選択肢問題) | |
| 問8 | 会話文内の指示語が指す内容(記述問題・20字以内) | |
| 問9 | 会話文の内容に対応する情景描写(書き抜き問題) | |
| 問10 | 登場人物の心情説明(選択肢問題) | |
| 問11 | 登場人物の人物像説明(記述問題・50字以内) | |
| 問12 | 指示語の指示内容(選択肢問題) | |
| 問13 | 登場人物の人物像説明(選択肢問題) | |
| 大問2 | 本文内容 | 論説文(石浦章一『日本人はなぜ科学より感情で動くのか 世界を確率で理解するサイエンスコミュニケーション入門』より) 環境問題を話題としながら複数の視点を持って議論することの必要性を訴える内容 |
| 問1 | 漢字の読み書き(書き1問・読み1問) | |
| 問2 | 本文内容を説明した表の空所補充(2問・それぞれ3字の書き抜き問題) | |
| 問3 | 「外来種」についての筆者の見解をまとめた文の空所補充(記述問題・30字以内) | |
| 問4 | 本文中の接続語の補充(選択肢問題) | |
| 問5 | 本文中の空所の補充(選択肢問題) | |
| 問6 | 本文中の「海」についての説明(選択肢問題 ※あてはまらないものを選ぶ) | |
| 問7 | 傍線部の理由説明(記述問題・50字以内) | |
| 問8 | 「段落の働きを説明した文」に合う段落の指摘(段落番号を選択する問題) | |
| 問9 | 文章全体の内容説明(選択肢問題 ※本文内容に合っていないものを選ぶ) | |
| 問10 | 【作文】「二つの別々の考えがあるものを皆で議論してどうしたらいいかを決めることが重要だと感じたとき」に 「どのように行動したか」を書く(200字以上250字以内) |
算数
(40点満点・40分)
1.重要単元は4つの単元
① 規則性に関する問題 ② 速さに関する問題
③ 平面図形に関する問題 ④ 場合の数に関する問題
この4つの単元については、近年よく出されている問題です。
基本的な内容が中心ですが、問題数がかなり多く、試験時間が短いので、時間配分に注意する必要があります。
2024年度、初めて説明する問題が出されましたが、2025年度は出題されませんでした。
2.大問2の小問集合は4年生の内容も出題される
大問2の小問集合では小4で学習する大きな数・概数・面積の単位変換などがよく出題されます。
他にも多角形の角度や対角線の本数・人口密度・対称図形など幅広く出題されます。
3.グラフを使った問題がよく出される
速さや水量変化の問題は、グラフを使った問題がよく出されます。
2025年度はグラフの問題は出ませんでしたが、今後も出題される可能性が高いです。
4.大問1の計算問題では、くふうが必要な問題も出される
最近では、大問1の計算問題でくふうが必要な問題がよく出されており、2025年度も出題されました。
難易度も徐々に上がってきているので、私立中学校で出題されるような計算問題も解けるようにしていきましょう。
| 大問番号 | 小問数 | 内容 |
|---|---|---|
| [1] | 4 | 計算問題 |
| [2] | 10 | 小問集合 |
| [3] | 2 | 時計算 |
| [4] | 2 | (1)場合の数(2)比例 |
| [5] | 2 | 通過算 |
| [6] | 2 | 暦算 |
| [7] | 5 | いろいろな正方形 |
理科
理科・社会合わせて40分、40点満点。
理科は15分~20分程度、20点満点。
20分で20問、すべて記号選択の問題になっていることもあり、ややこしい選択肢も多く見られます。
選択肢のグループ分けや、選択肢の間違っている部分を見つけ消していく、というような作業をしながら解いていく必要があります。
2025年度は、 物理5問、 化学5問、 生物5問、 地学5問と、4分野が均一に出題されました。
| 大問番号 | 小問数 | 内容 |
|---|---|---|
| [1] | 6 | 小問集合(正誤問題) |
| [2] | 4 | 月の満ち欠けについて |
| [3] | 3 | 水溶液の性質について |
| [4] | 3 | 植物のはたらきについて |
| [5] | 4 | ふりこについて |
社会
理科・社会合わせて40分、40点満点。
社会は20分程度、20点満点。
地理分野7問、歴史分野8問、公民分野4問の合計19問で、うち4問が短文形式の記述問題(地理1問、歴史2問、公民1問)が出題されました。
各分野の出題傾向は下記の通りです。
・地理分野:日本の国土や産業など、テーマをしぼって出題。
・歴史分野:幅広い時代の人物や出来事についての正誤問題。
・公民分野:日本国憲法や基本的人権などについて出題。
地理・歴史・公民分野ともにグラフや図、写真などの資料が多用されるので、その読解力も求められます。
| 大問番号 | 小問数 | 内容 |
|---|---|---|
| [1] | 8 | 平安時代、鎌倉時代、江戸時代の政治や文化に関する問題 |
| [2] | 7 | 都道府県、日本の国土や産業、国旗に関する問題 |
| [3] | 4 | 国会、内閣、選挙に関する問題 |