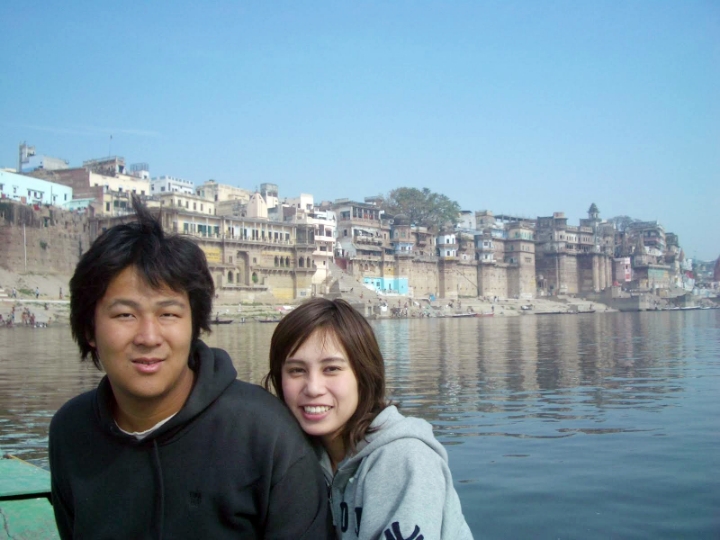空気が読めず、
友達がいなかった子ども時代
「どうして僕には親友がいないんだろう……」。意外に思うかもしれないが、少年時代の小椋は孤独だった。昼食を食べるのも、学校内を移動するときも、たいてい一人。みんなはそれぞれ仲良しグループがあるのに、自分だけそのどこにも入れない。
別にシャイだったわけでも、無視されていたわけでもない。むしろ明るかったし、少年らしい無邪気さもあった。なのに「親友」と呼べる人も、呼んでくれる人もいない。友達が向こうから寄って来てくれるわけでもなく、自分が寄って行けばその分友達が引いていく。常に一定距離を保たれて、それが永遠に埋まらない。「浮いていた」というのが、最もぴったりくる表現だろう。「さびしいな……」。いつもそんな思いを胸に抱えていた。
実は小椋は、「空気が読めないタイプ」だった。ちょっと度を越してふざけてしまうところがあって、それで煙たがられてることに気付かず、さらにふざけ続ける。周りからすれば、面倒な存在だったのだ。大人になった小椋は、そう苦笑しながら自分を振り返る。
ただ、その空気の読めなさは、同時に強い正義感も形成していく。中学生のころには、学食の行列に横入りする先輩に「後ろに並べや!」と臆することなく咎める若者になっていた。やがてKECに入社し、激しい反発や造反を招きながら大改革を断行したのも、「敬愛する父が創り、自分も生徒として学んだ大好きなKECが、このままではダメになる!」という一心からだった。人として正しくあろうとするKECマインドも、現代教育に疑問を抱き、新たな教育価値を創造しようとしているのも、すべてこの正義感に由来していると言っていい。